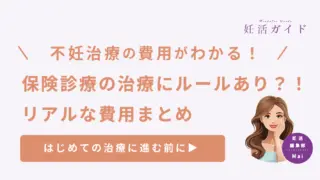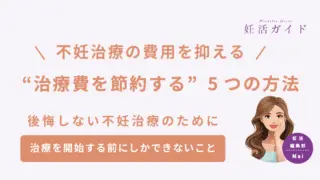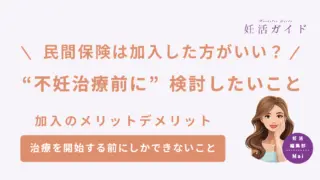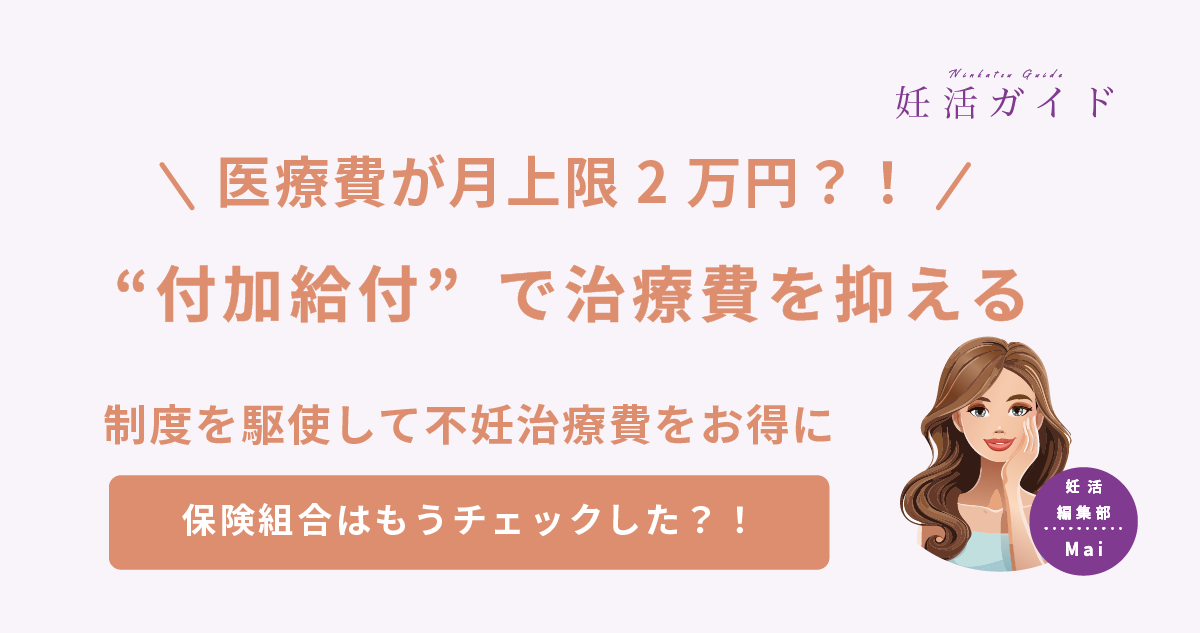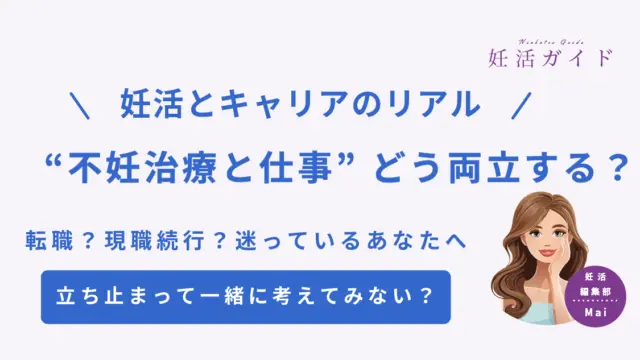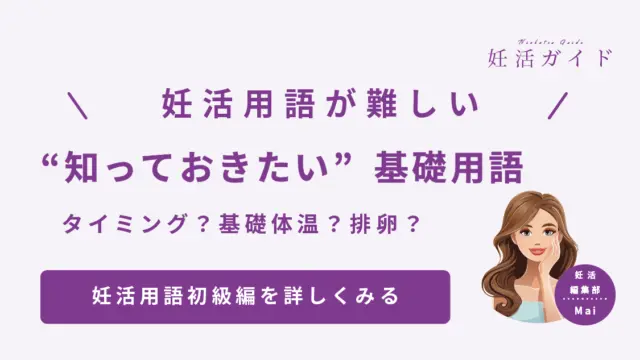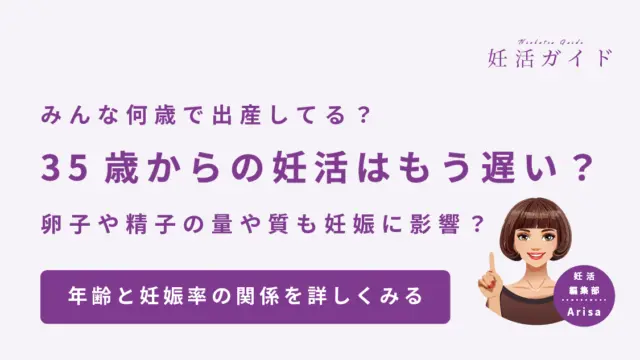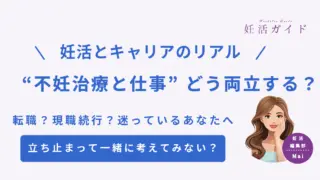「付加給付制度」とは?
- 健康保険組合が設けている独自の補助制度
高額療養費制度では、一定額を超える医療費について一部が払い戻されますが、付加給付制度ではさらに上乗せしてカバーしてくれる仕組み。たとえば、月の自己負担が「2万円まで」と決められている場合、それを超えた分は全額戻ってくることもあります。
- 実質自己負担がかなり抑えられる可能性がある
不妊治療や手術など、まとまった医療費がかかる場面ではとくにありがたい制度です。高額な治療も「実質的な支出」を大きく減らせる可能性があるため、積極的に活用すべき制度のひとつです。
- 付加給付制度があるのは一部の組合だけ
すべての健康保険でこの制度があるわけではありません。全国健康保険協会(協会けんぽ)には基本的に付加給付制度はなく、大企業などが設けている「組合健保」に限定されるケースが多いです。
- 組合により内容は異なるので要確認
給付の対象となる医療費の範囲や、自己負担上限額などは各健康保険組合によって異なります。加入している保険証に記載された組合名で検索し、公式サイトや人事・福利厚生窓口などで詳細をチェックしましょう。
どんな不妊治療が「付加給付制度」の対象になるの?
- 保険診療に該当する不妊治療であれば対象になることが多い
付加給付制度の対象になるのは「健康保険が適用される医療費」に限られます。たとえば、体外受精・顕微授精の一部(採卵・培養・胚移植など)は2022年から保険診療になったため、対象に含まれる可能性があります。
- 自費診療(自由診療)は対象外
先進医療やオプション的な検査(タイムラプス培養、ERA検査など)は保険が効かないため、付加給付制度の補助対象にはなりません。
- 入院・手術・検査費も対象となるケースあり
子宮筋腫やポリープの切除手術、不妊治療前の検査入院など、保険診療扱いのものは対象になる可能性が高いです。
どれくらい戻ってくる?自己負担の具体例
- 高額療養費制度のみの場合:
例)医療費総額 100万円/自己負担3割 → 30万円
年収400万円程度の「区分ウ」では、自己負担上限が約82,430円になるケースも。 - 高額療養費制度+付加給付あり:
組合によっては「自己負担は2万円まで」などの補助がある。残りの6万円以上が給付対象になる可能性も。
付加給付が手厚い企業・健保の例
| 健保名/組織 | 上限額の目安 | 特徴 | 補足 |
|---|---|---|---|
| トヨタ健康保険組合 | 20,000円/月 | 1人・ひと月(1日~末日の受診)・1医療機関単位かつ、入院・外来・歯科単位で算出 | 詳細は公式にて要確認 |
| NTT健康保険組合 | 25,000円/月 | 1人・ひと月(1日~末日の受診)・1医療機関単位かつ、入院・外来・歯科単位で算出 | 詳細は公式にて要確認 |
| ANA健康保険組合 | 25,000円/月 | レセプト1件毎に25,000円を控除した額を支給 | 詳細は公式にて要確認 |
| 公務員共済(国家・地方) | 2.5〜5万円/月 | 1人・ひと月(1日~末日の受診)・1医療機関単位かつ、入院・外来・歯科単位で算出 | 詳細は公式にて要確認 |
| 協会けんぽ | ―(なし) | 付加給付制度は基本的に存在しない | 高額療養費制度のみ適用 |
- Q. 付加給付制度の「上限額」って、どうやって決まるの?
A. 多くの健康保険組合では「1医療機関」「1種類の診療区分(外来・入院・歯科)」ごとに月額上限が定められています。同じクリニックでも、外来と入院では別枠としてカウントされることがあるため、要注意。 - Q. 実際の負担額ってどれくらい?
A. 例:
・Aクリニック(外来)+Aクリニック(外来手術)
→ 上限2万円までで収まる可能性・Aクリニック(外来)+Aクリニック(入院手術)
→ 外来2万円+入院2万円=上限4万円となる可能性・Aクリニック(外来)+Bクリニック(手術)
→ 病院が異なるため、それぞれで上限が設定される(2万円+2万円=計4万円など)診療区分や病院の違いで実質負担金はかなり違ってくるので通院開始前に検討しておくと安心です。
加入健保の確認方法
- 保険証を確認する
健康保険証の表面に記載されている「保険者名」「保険者番号」を見れば、あなたが加入している健保の名称が分かります。
- 名称を検索して公式サイトへ
記載の保険組合名を「◯◯健康保険組合 付加給付」などで調べる。
- 社内の人事・福利厚生担当に相談
健保の制度がWebで見つけにくい場合は、人事部門に聞くのが確実。会社独自の案内資料を持っている場合もあります。
付加給付があると選択肢が広がる!
- ご自身の会社に制度がなければ、付加給付が充実した企業への転職も視野に。
- パートナーの健保に手厚い制度があれば、扶養に入る選択もあり得ます。
- どちらも「今すぐに」というよりも、ライフプランの中で柔軟に検討するのが◎。
まとめ:付加給付制度を味方につけて、不妊治療をもっと安心に
- 付加給付制度は「組合健保」ならではの追加補助制度
- 保険診療の不妊治療であれば対象になる可能性が高い
- 加入健保ごとに内容が違うので、必ず確認を
- 状況によっては転職・扶養変更なども検討材料に