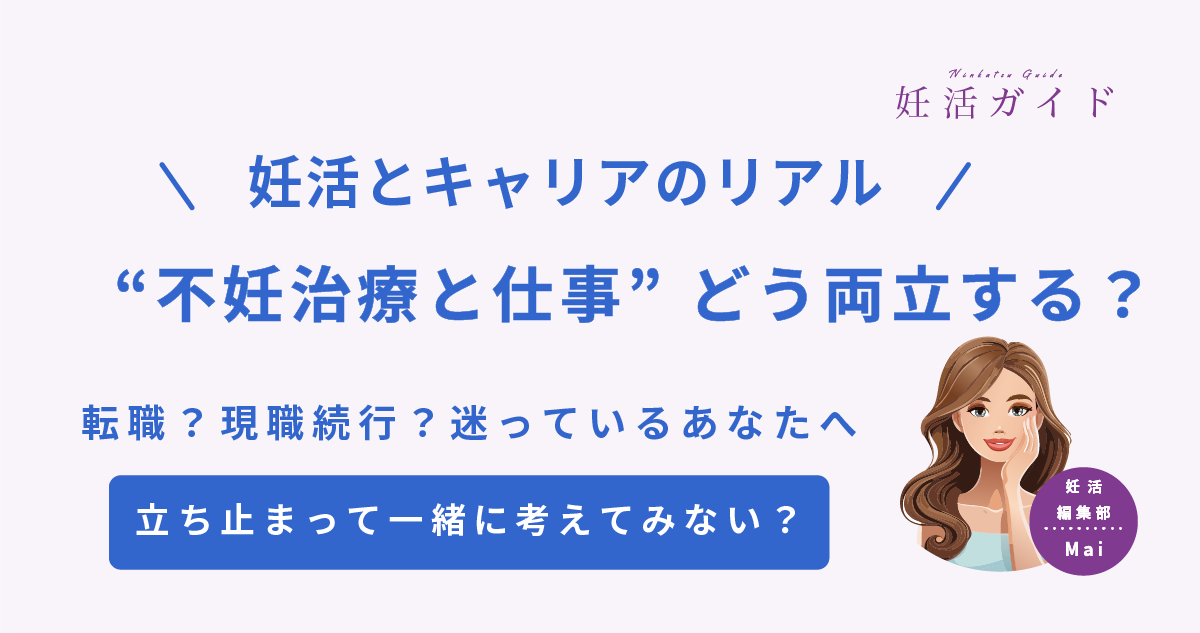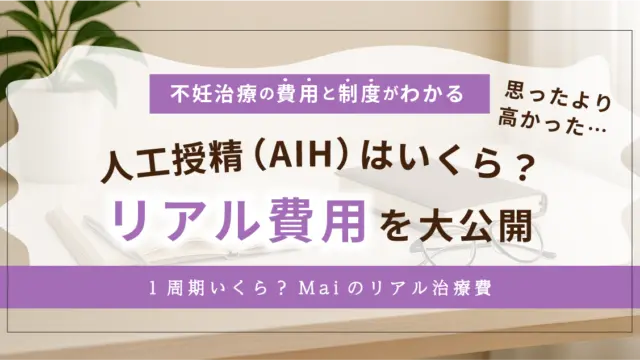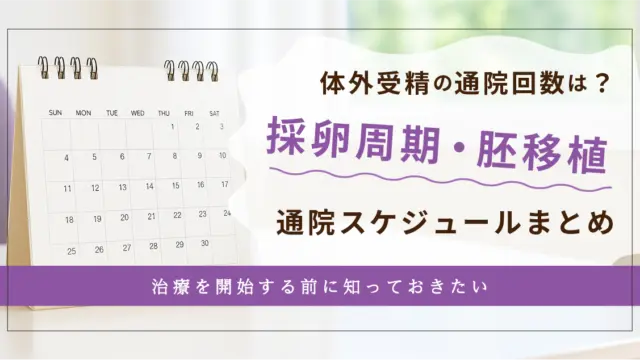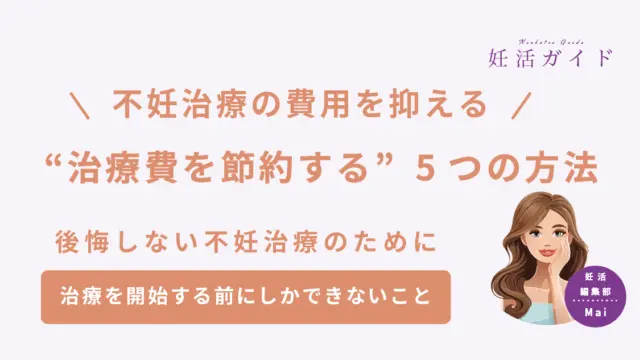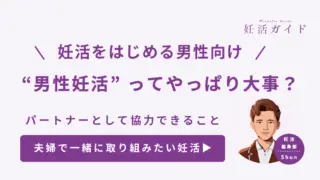Contents
妊活と仕事の両立が難しい理由とは?
「仕事と妊活、両立したいけど……結構ハードルが高い気がしてしまう…。」
「そうね。不妊治療は自分のペースではなく身体のペースで行われるものだからスケジュール調整はものすごくストレスなのよ。」
不妊治療と仕事チェック
- 通院スケジュールが直前に決まりがち:予定が立てづらく、急な休みが必要になることも
- 体調不良や副作用が起きやすい:当日出勤が難しくなるケースも
- メンタルの浮き沈みが大きい:集中力が続かない日もある
- 妊活を職場で言い出しづらい:孤独感や理解されないストレスが生まれやすい
一人で悩まないで。福利厚生を確認しよう
「でも職場にはいいづらい…。何とかならないかな…。」
「センシティブな話だから気持ちはわかる…。でも一人で抱え込まないでね。最近は不妊治療の理解も進んでいて、福利厚生でカバーしてくれる企業も増えているの。まずは人事やポータル情報を確認してみて。」
福利厚生チェック
- 付加給付制度がある健康保険組合か:医療費の実質負担が大きく変わる
- 不妊治療のための休職・休暇制度がある:診断書などで取得できる制度も
- 治療費の補助制度がある:会社独自で助成金を設けているケースも
- 時短勤務・フレックス制度が使える:通院スケジュールに合わせやすくなる
- 職場の風土に理解があるか:上司やチームのサポート体制も重要
産休育休のために頑張ってきたあなたへ
「正社員のままだと通院が本当に大変…。かといって、仕事を辞めるのも不安だし…。」
「日本では、産休・育休といった制度があるからこそ、正社員で頑張ってきた方も多いと思うの。でも、不妊治療と仕事の両立が本当に難しい場合、選択肢を見直すタイミングかもしれないわ。」
「産休と育休のために正社員で頑張ってきたけど、不妊治療との両立がこんなに大変だなんて…。本当に悩むなぁ。」
「もちろん今の職場で頑張るのもいい。不妊治療に理解のある会社なら子どもがいる家庭への配慮もあると思うの。でもそうでないなら妊娠して子どもが産まれたら転職しづらくなる。であれば今のうちに転職を検討するのも一つの選択肢よ。」
柔軟に働ける環境チェック
- テレワークやフレックス制度がある会社を選ぶ:通院のスケジュールに合わせやすい
- 有給や半休が取りやすい職場かを確認:急な通院対応に備える
- 妊活に理解のある上司・チームか:精神的ストレスを減らす要素に
産休・育児休暇の条件
「転職しちゃったら産休や育休がもらえなくなるんじゃない…?」
「転職したら育休が絶対もらえないわけじゃないのよ。法律が変わって、勤続1年未満でも育休申請できる道が開かれたの。」
| 比較項目 | 産休 | 育休 |
|---|---|---|
| 取得条件 | 雇用形態・勤続年数に関係なく取得可能 | 原則「1年以上勤務」が条件だったが、2022年改正で勤続1年未満でも取得可能に ※ただし労使協定で対象外となる場合あり |
| 取得可能期間 | 出産予定日の6週間前〜出産後8週間まで (多胎妊娠は14週間前から) |
原則子どもが1歳になるまで 条件により1歳6か月・2歳まで延長可能 |
| 給付金・手当 | 産前産後休業中は給与なし 健康保険から「出産手当金」が支給される |
雇用保険から「育児休業給付金」が支給 開始〜6か月は賃金の67%、それ以降は50% |
| 申し出時期 | 出産予定日の1か月前を目安に申請 | 休業開始の1か月前までに申請が望ましい |
| 対象者 | 女性(産前産後休業) | 男女とも取得可能 |
※詳しくは 厚生労働省の「妊娠・産休・育休 特設コーナー(労働者の方向け)」 ページをご確認ください。
Q&A
- Q. 産休と育休は誰でも取得できる?
A. 産休は勤続年数や雇用形態に関係なく取得可能です。一方、育休は原則「1年以上勤務」が条件でしたが、法改正で勤続1年未満でも取得できるケースがあります。ただし会社の労使協定によっては例外もあるので、必ず就業規則を確認しましょう。 - Q. 育児休業給付金はいくらもらえる?
A. 雇用保険から支給され、育休開始から6か月までは給与の約67%、それ以降は50%が目安です。上限額があるため、高収入の場合は満額の給与にはならない点に注意が必要です。 - Q. 男性も育休を取れるの?
A. はい、法律で男女ともに取得可能です。最近は「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度もでき、分割して取得できるなど柔軟性が増しています。
転職すべき? 見極めたい“働き方”の限界と選択のタイミング
「今の職場でやっていきたいけど、制度がないし、正直限界を感じてる…転職したほうがいいのかな?」
「転職は大きな決断だけど、今感じている “違和感” を無視しないことも大事。迷ってるなら、まず“今転職すべきタイミングか”をチェックしておきましょう。」
転職を考えた方がいい?
- 制度がまったく整っていない:妊活や育休・休暇制度の情報が見当たらない
- 相談窓口が機能していない/理解されない:人事や上司に相談しても取り合ってもらえない
- 通院や治療両立が物理的に難しい: 通院回数が増えて仕事の調整が限界
- 心身の負荷が大きくなっている:メンタルや健康面で影響が出始めている
「私の知り合いも、通院と残業で体力的に限界になって、思い切って転職したら制度が手厚くて救われたっていってたなあ…」
「妊活のメンタルっていきなりポッキリいくこともあるからすごくわかる。でも環境を変えるストレスもあるから今の職場で頑張るのもあり。ただ仕事場はそこだけではないことを頭に入れておくと少し安心できると思う。」
Q&A
不妊治療が大変だから「今、絶対に転職した方がいい」わけではありません。
今いる職場で調整できる可能性が残っているかを見極めつつ、将来的に「安心できる職場」へ移る道を知っておくのがおすすめです。
みんなどうしてる? 妊活と仕事、リアルな“選択肢”
「結局不妊治療をしている人はどのような仕事と治療の両立の道を選んでいるんだろう?」
「気になるわよね。以下の表を見てみて。特に不妊治療が長引くと選択を迫られがち。そうなる前に未来の自分をイメージすることが大切よ。」
| Before | After | 選択理由・状況 | メリット/デメリット |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 同じ職場で治療継続 | 上司に相談し、可能な範囲で治療と両立することに | ◎収入安定 / △スケジュール調整が必要 |
| 正社員 | 転職 | 激務だったため、不妊治療をきっかけに転職 | ◎心の余裕ができた / △給与がややダウン |
| 正社員 | 専業主婦 | 期間を決めて治療に専念するため退職 | ◎メンタル安定 / △収入ゼロの不安あり |
| 契約社員 | 正社員に転職 | 産休・育休も視野に安定を重視 | ◎福利厚生充実 / △業務量の増加が懸念 |
| 派遣社員(週5) | 派遣社員(週3) | スケジュールに余裕をもたせるため | ◎通院と両立しやすい / △収入ダウン |
「こうやって比較すると色々な選択肢があるね。」
「不妊治療は立ち止まって考えることのできる時間でもあるわ。そして人によって正解も違うの。だからあなたの正解をこの機会に考えてみてほしい。しっかり考えた答えはどれも正解のはず。」
妊活は「働き方」と一緒に考える時代へ
「なんだか少し視界が開けたかも…。妊活と仕事、どっちも自分の大事なことだよね。」
「うん、自分の人生に合わせて“働き方”を選ぶことは、決してわがままじゃないの。妊活はライフプランの一部。もっと柔軟に、もっと自分らしく選んでいいと思うわ。」
妊活と仕事、どちらも大切にするために
- まずは今の職場の制度をチェック:知らなかったサポートがあるかも
- 無理せず、自分の限界を見極めて:心と体の声に耳を傾けて
- 転職も選択肢のひとつ:妊活しやすい職場環境へ、今のうちに考える
※本情報は研究データに基づく参考情報であり、個別の診断・治療を目的としたものではありません。
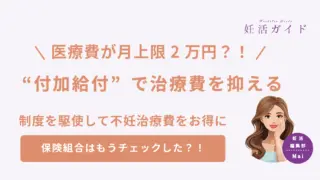
【保存版】知らなきゃ損する“付加給付制度”とは?不妊治療費が劇的に変わる!「付加給付制度」とは?
「会社の健康保険で“付加給付”があるって聞いたんだけど、それってどんな...
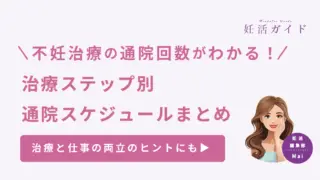
【はじめての不妊治療】通院頻度はどれくらい?タイミング法・人工授精(IUI)の流れまとめタイミング法・人工授精(IUI)の通院頻度はどれくらい?
「不妊治療で通院することに決めたけど、...